もう食品会社に入社して3年目になりますが、ふとKindleにあった、「1年目の教科書」という本を最近読みました。この本は「1年目の時に社会人になるにあたって、何が大切かを知りたいな」と思って買った本なのですが、久しぶりに見てタメになったので、今日はそれを紹介します。
久しぶりに読んだけど、1年目の教科書は1年目じゃなくてもタメになる。
たまに見返すと、仕事を進める上での本質を見失ってたなぁと思うことがあります。
①頼まれたことは必ずやりきる
②50点でいいから早く出せ
③つまらない仕事はない③はいつも心がけていますが、①と②は忙しいとおろそかになってしまいがち。この本、入社一年目じゃなくても役立ちますよ。 pic.twitter.com/eZISGKIwAb
— となりの余白🐣 (@hiyokon_banana) 2019年5月24日
1年目の教科書の最初に、「仕事の原則」が3つのっています。
その3つがこんな感じ。
①頼まれたことは必ずやりきる
②50点でいいから早く出せ
③つまらない仕事はない
社会人になって丸2年が経ちましたが、この3つは本当に大切だなぁ、と普段の仕事を通しても感じます。
仕事の原則1:頼まれたことを必ずやりきる
これができる人って、周りから群を抜いて仕事ができる人として評価されます。
なぜかというと、「実行すること」が会社に求められているし、それをやりきる人が「会社の利益を上げている」からです。
つまり、その人がいるから、会社が儲かるんですよね。実行力がないと利益は生まれない。そう思っています。これはフリーランスにも言えることだと思いますが、やると決めたこと(それが自発的であれ、人から頼まれたことであれ)を最後までやりきる力はどんな仕事についても必要です。
「岩瀬、新人のうちは頭が良いとか優秀だとかいうのは、どうでもいいことなんだよ。
上に頼まれた仕事を何が何でもやりきってくれるかどうか。仕事を頼む側からすると、最も大事なことはそういうことなんだよ。」(1年目の教科書/岩瀬大輔(ダイヤモンド社)より)
頼まれたことは何があっても絶対にやりきる。自主的に、催促される前に全部やりきる。その積み重ねで周囲から信頼に足る人物だと評価されれば、次の仕事が回ってきます。そうして経験値を重ねていけると、仕事の幅が広がり、また仕事が回ってきます。大変なように思えますがそれをこなしていくことで仕事の質も量も上がって、どんどん成長できるというのがこの原則です。
仕事の原則2:50点で構わないから早く出せ
聞くことは恥ではないという考えを早い時点で持つべきです。僕もこれがうまくできずに叱られることが何度も今までにありました笑。結局は聞いて軌道修正を早い段階でしたほうがあとあとうまくいくんですよね。結局は経験のある人や上司にフィードバックをもらった方が絶対に良いです。
正解がないからこそ、最適解を早めに知る手段として上司からフィードバックをもらうのはとても大切なことですし、ベンチャーだとなおさら知らないなりに聞くことが大切だと思います。フリーランスでもこの力は大切なんじゃないかな。
仕事の原則3:つまらない仕事はない
一番単調な仕事でも、見方を変えることによって、向き合う仕事は全く違うものとして見えてきます。議事録だったら、その意味と目的を知れば、様々な工夫ができます。僕自身、メモをしてその内容を100文字で簡潔にまとめる、みたいな要約の練習として使ったこともありますし、会議に参加していない人のために書く議事録という名目で詳しく、かつわかりやすく作ろうと努力した時もあります。
会議の参加者の記憶を残すために使うのか。それとも会議を受けて次に進むべきステップを検討するために使うのか。ディスカッションした内容から新たな言葉を生み出すために使うのか。その目的を把握することで工夫をすることができるので、どんなに単調な仕事でも、面白くない仕事はないと思います。
仕事は1年目も2年目も関係なく原則があると思わせてくれる。
この本は、そんな仕事の原則を教えてくれる本です。久しぶりに読んで初心に戻れたような気がします。
仕事で悩んでいるときこそ、初心に戻ることも大切なのかな、と思わせてくれました。
となりの余白
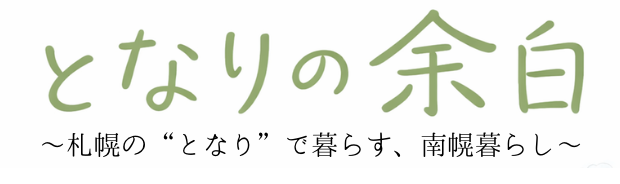
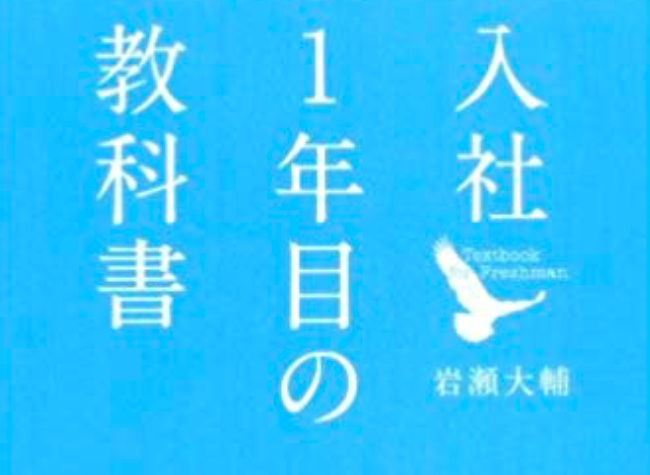
前の記事
次の記事